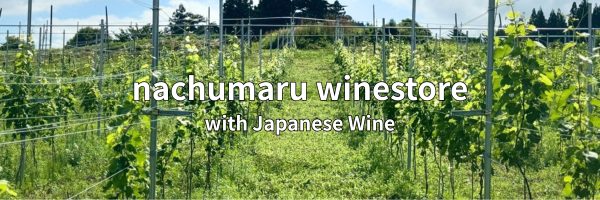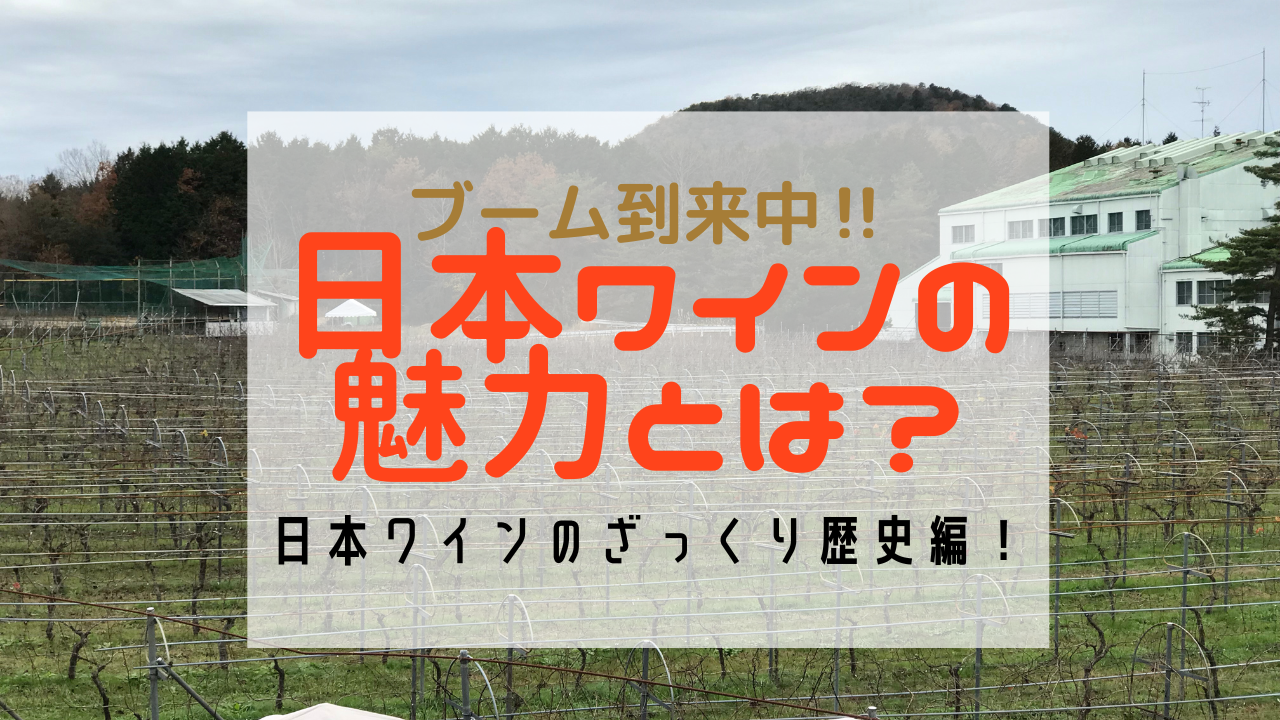日本ワインが雑誌やメディアで多く取り上げられているけど何故だろう?今からでも遅くない!日本ワインの魅力って?知るとおもしろい日本ワイン!
約140年かけて進化する日本ワイン ~日本ワインざっくり歴史編~
1.最初の日本ワイン作りは失敗の繰り返し
日本でワイン作りを始めたのは約140年前。明治4年頃、甲府の青年二人が書物と横浜にいた来日外国人からワイン造りの知識を学び醸造を試みたのが始まりです。
順調に思えた日本ワイン初醸造の挑戦ですが、徐々にワインに劣化が起き始めます。原料ブドウの糖度不足と醸造技術の未熟さ、防腐未処理が原因で売り物にならず失敗に終わってしまいます。
6年後の明治10年、山梨に日本初のワイン会社が設立します。その後、日本ワイン作りが広まり始め、川上善兵衛氏が日本の気候に合わせブドウ品種の改良を行ったり、明治政府が外交政策として日本ワイン作りの支援を開始します。また、当時の若手投資家達がワイン事業に好機を見出し多額の投資を始めていきます。
次々と新規ワイナリーが設立され日本中にワイン文化が広がるか勢いでしたが、当時のヨーロッパを手本としたワインは酸味が強く、日本人の食生活になかなか受け入れずワイン文化の定着は停滞していきます。
2.ついに来たか⁉日本ワインブーム!!
低迷する日本ワイン産業50年に転機が訪れるのは昭和39年頃。東京オリンピック開催と大阪万博の開催に伴って日本中に洋食を提供する店が増え、食中酒としてワインが日本人に受け入れ始めていきました。しかし、日本の急激な食の欧米化は輸入ワインに人気を集め、日本ワインブーム到来!とは行きませんでした。
3.輸入ワイン人気が日本ワインにもたらす恩恵とは!?
平成に入り『本場の味』の輸入ワインが日本中に増え、数百万円の高級ワインから数百円の安旨ワインが手に入るまでに広まり、ワイン文化が定着していきます。無類のワインLoverが増え、日本でもワインに対する価値観やリテラシーが育まれていきます。海外ワインと比較されるようになった日本ワインの作り手達は、味や価格、エチケットデザインなど多くの刺激を受け、日本ワインに取り入れていきます。
4.グローバル化とSNSが日本ワインを急成長させる
インターネットの発展により海外製の醸造用機器や備品、栽培と醸造の専門的な情報も手に入れやすくなり、欧米各国に引けを取らないワイン作りができるようになりました。
近年、世界中で『自然派ワイン』と呼ばれる環境に配慮した農法や醸造スタイルのワインがブームとなり、エチケットも個性的なデザインが多く、SNS上で『映える』ものが人気を集めいます。
日本でも土地柄の特性や風土を表現し、作り手自身の個性を活かした様々なスタイルでお洒落なデザインのワインが増えています。
5.令和の日本ワイン
現在ではワインを作る工程が見え、その場で樽出しワインが飲める『クラフトワイナリー』『マイクロワイナリー』などの都市型ワイナリーが注目されています。
対して創業100年を超える老舗ワイナリーでも微発泡ペティアンスタイルのワインをリリースするなど、世代交代が起き、古き良きを伝統を守りながらも新しい挑戦を続けています。
6.まとめ
2023年も王冠を使用した微発泡ペティアンスタイルのワインや『自然派ワイン』の人気は変わらずですが、SNSの『映えワイン』から『物語のあるワイン』に注目が移ってきています。是非、皆さんもお気に入りの『語れるワイン』を色んな所で見つけてほしいと思います。